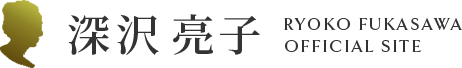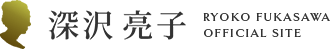メッセージ MESSAGE
ピアノは私にとって大切な友達であり人生そのものです。
両親も音楽が好きで、特に父は子供の頃から本格的にピアノとフルートを勉強し、大学生の頃は新交響楽団(N響の前身)のエキストラも務めたようです。専門は心理学でした。母も3人の子供を育てながら物のない時代、私達が喜んで食べられるおかずを工夫したり、私や親せきの子供達へも洋服を縫ってくれました。木綿の紺色の風呂敷で白い衿をつけてワンピースを作ってくれたのを覚えております。工夫の上手な心の温かい母でした。夕食後、父が使っていたヤマハのアップライトピアノで、両親がDuo(父はフルート、母はピアノ)を楽しそうに練習しており、私は傍らで2人の練習を聴きながら遊んでいたそうで、3歳位の時、「ピアノを教えて」と両親にせがんだと父から聞いております。その後、2年生の時、父の恩師永井進(ながいすすむ)先生に聴いて頂きましたが、「まだお父さんでいいでしょう」とおっしゃり、父の背中をポンとたたかれ、小学4年生で先生に見ていただく様になるまでは両親に教わりました。
戦中戦後は大変な世の中で、ピアノの音が出せない日もありました。東京から女学生の方々が東金へ疎開され、よく我が家のお風呂へ入りにこられたり、兵隊さんが立ち寄ったりし「亮子ちゃん、ピアノ聴かせて」と言って下さり、私のピアノを皆さんが喜んでいらした様子は、私にとって励みになった事を覚えております。終戦後はまだまだ世の中の混乱が続いておりましたが、今思えば、この様な時だからこそ、音楽や絵画、スキー等の好きな方々が時々我が家に集まり、皆で合奏やコーラスをしながら、心の豊かさを保っていた事が思いだされます。その後、母も少しずつ好きな絵を描いたり、短歌を作ったりしはじめました。この様な環境に育ったせいか、私も自然に音楽が好きになり自発的に練習もする様になりました。
4年生より、永井先生が正式に生徒にとって下さる事になり、その年、先生のお勧めにより学生音楽コンクールを受け2位を頂き、又2年後6年生でメンデルスゾーンの「17の厳格なる変奏曲」を弾いて全国1位になり、少しずつ将来はピアニストになりたいと言う気持ちが芽生えてきた様でした。
中学3年生の時に先生が「大人のコンクール(現在の日本音楽コンクール)を受けてみないか」とおっしゃり、その年の夏休みは猛勉強を致しました。
東金から片道3時間もかかる目白の先生のお宅まで伺い、度々レッスンして頂き思いがけなく優勝。
 課題曲は
課題曲は
第1次、ベートーヴェン・作品111の1楽章
第2次、バッハ:平均律より1曲
下記の5曲から当日くじ引きで当たった曲を弾く
ショパン:舟歌・スケルツォ3番
リスト :超絶技巧用練習曲 No.10
ドビュッーシー:‘ピアノのために’より
「トッカータ」
ラヴェル:道化師の朝のうた
本選はその後1か月後にあり、2次が終わった後で発表になりました。曲は下記の通りでした。
ショパン:エチュード作品25 No3,4,11「木枯らし」
その他、自由曲が1曲
私はシューマンのプレスト・パッショナータを弾きました。
ところが本選の前々日に運悪く右の小指の先がヒョウソで真っ白な膿がたまり、ショパンのエチュード「木枯らし」の練習を始めましたら(1曲通して弾こうと思ったのです)、5の指が鍵盤に触れるだけで痛くて痛くて弾けませんでした。あまりの痛さに棄権したいと先生のお宅へ叔母と2人で伺いました。先生には「馬鹿野郎!何考えてるんだ!」と大きな声でしかられ、私は先生がそうおっしゃるのなら「やってみよう!」と思い直し、外科医の叔父に相談し切開して膿をだしてもらい、日比谷公会堂で弾く事ができました。無我夢中でした。叔父も翌日に演奏できるよう随分手術の方法を考えてくれたと後日知り、感謝の気持ちでいっぱいでした。きっと神様が守って下さったのでしょう。大人のコンクールは学生コンクールの時と異なり曲も多く何かと大変でしたが、先生や家族、学校の先生方もよく理解して下さり、皆様に励まして頂き、そして音楽の道へ進んだことは両親や多くの心温かい方々のお蔭だと今も感謝しております。
1週間後、両親と永井先生のお宅へご挨拶に伺いましたら、先生が「ごめん、ごめん。亮子ちゃんは歳は1番若かったけど、1次からずっと最高点だったんだよ。あそこで本選前に棄権されたらと思うと、我慢できなかったんだよ。それに君は欲がないから、あれくらい言わないと諦めてしまうと思ったのだよ」と、仰って下さいました。コンクール後のご褒美で、東京交響楽団とのウエーバーの「コンチェルト・シュテュック」を弾く機会を頂き、レッスンの時は、永井先生がピアノで伴奏を弾いて下さいました。実際、東京交響楽団の練習場で弾いた時は、オーケストラのホルンの響きが私へ迫ってきて圧倒されました。コンチェルトは初めてでしたが、本番の演奏も日比谷公会堂で思いきった演奏ができ、永井先生は笑顔で「君は得な性格だなぁ!本番になると普段よりも良い演奏ができていいね。僕なんか石橋を叩いても渡らない性格だからなぁ」と褒めて下さいました。先生は15歳から正式にピアノを勉強されたそうで、無論、持って生まれた才能も沢山おありになったと思いますが、ご努力を思い知らされたのは、先生のコンサートを何回かお聴きした時に感じたものでした。
コンクール入賞後、NHKの放送等があり、留学する為の試験を受けてパス。高校2年生の終わりウィーン国立音楽大学へ留学が決まり、当時は6年制でしたが3年生として入学、卒業後は大学院生として2年間在学致しました。ウィーンでは着いて直ぐ、声楽家の佐々木(ささき)成子(さだこ)先生にチケットの買い方を教えて頂き、殆ど毎日のように、ムズィークフェラインやコンツェルトハウス等で音楽会を聞いたり、国立オペラ劇場でオペラを鑑賞致しました。また日曜日には(日曜日は安息日で、音を出してはいけない日と決まっていて、ピアノの練習はできなかったのです)美術館や博物館へも通い絵画や彫刻等を観、楽しいことが沢山あり、いろいろなことを吸収できました。
10代後半に本物に触れ、観たり聴いたりできたこと、由緒ある素敵なホールや宮殿等で何度も演奏できた事は光栄であり、何にも代えがたい勉強と経験になりました。6月の音楽祭では、世界的なピアニストで、私が留学前に東京で演奏を聴いて頂き、その後のコンサートでは素晴らしい演奏を聴く事のできたW・バックハウス、世界的な指揮者ブルーノ・ワルターやピアニストのクララ・ハスキル等、沢山の演奏を聴き、深い感銘を受けました。
まさに黄金時代でした。

私がウィーンで師事したG・ヒンターホーファー教授はリストのお弟子、E・ザウワーの生徒でいらしたので、私はリストのひ孫弟子となります。ウィーンは古い歴史のある落ちついた美しい町で、音楽は勿論、絵画、文学、演劇、建築等見るもの聞くもの全て感動するばかりでした。沢山の心ある知人、友人にも恵まれました。
楽友協会付属のコーラス団‘ズィングフェライン’も試験を受け、3年程、カラヤンやベーム他、世界の著名な指揮者のもと、フィッシャーディスカウ等名歌手達の近くでバッハの「マタイ受難曲」「ヨハネ受難曲」「h-mollのミサ」、ハイドン「天地創造」「四季」、ベートーヴェン「第9」「ミサ・ソレミニス」、ブラームス「ドイツレクイエム」他、沢山の宗教曲をソプラノの一人として、ウィーンやザルツブルグの音楽祭で歌い貴重な経験を致しました。
20歳を過ぎた頃、ムズィークフェライン「ブラームス・ザール」で初めてのリサイタルを行い、思いがけず12誌より絶賛されたり、ガスタイン賞(ウィーン国立音楽大学内にてバート・ガスタイン音楽祭でコンチェルトの出演者を決めるコンクールがあり優勝)を頂き、リストのピアノ・コンチェルトNo1を演奏。バート・ガスタインでは豪華なホテルで1週間滞在し、コンサート出演後はProf.バックハウスご夫妻と再会する事となりました。
Prof.バックハウスにはシューマンのコンチェルトを聴かせて頂き、アンコールはシューマンの「ヴァルム?(なぜ?)」でした。大変感銘を受け、又、思いがけなくご夫妻と再会でき、泊まっていらしたペンションでお茶までご馳走になり、日頃の練習方法等もお聞きすることができましたことはとても楽しく有意義なひと時でした。
翌年の春、ある日突然学長Dr.ズィットナー先生に呼ばれ、3週間のコンサートツアー(ドイツのミュンヘン、ケルン、シュトゥットガルト、デュッセルドルフ、フランクフルト、ハンブルグ、スエーデンのストックホルム、デンマークのコペンハーゲン、ベルギーのブリュッセル、ゲント)に参加するウィーン国立音楽大学の代表者の一人に選ばれ、嬉しく光栄に思いました。
代表者は、バリトン歌手、チェリスト、私の3名でした。私はソロと彼らのピアノ・パートを受け持ち、コンサートは毎回満席となり高評で、同行して下ったヒンターホーファー教授は私たち以上にとても喜んで下さいました。ウィーン国立音楽大学では、ピアノはソロとコンチェルトだけと言いう事はなく、他の楽器や歌とのDuo、室内楽も演奏する機会が度々ありました。秋には、ジュネーブ国際音楽コンクールを受け、結果はまた思いがけなく1位無しの2位となり優勝。スイス内の諸都市でご褒美の演奏会もあり良い経験となりました。
その後ウィーンへ帰り、ウィーン国立音楽大楽の学生で、国際コンクール入賞者達のコンサート出演致しました。会場はムズィークフェライン「黄金の間」、私はチャイコフスキーのコンチェルトNo1を演奏致しました。
N.Ö.トーンキュンストラー・オーケストラより初めて出演依頼があり、ムズィークフェライン「黄金の間」でメンデルスゾーンのコンチェルトNo1を演奏し、その後度々共演致しました。ホールの素晴らしい響き、楽器(ベーゼンドルファー)のすばらしさは今でも耳に残っており、その感覚を忘れた事はありません。
グラーツのコンサートへの出演は急に決まりました。ハンガリーの女流ピアニストE・ファルナディが急病になり、代役としてリストのコンチェルトNr.1を演奏。公演は2回でした。
 そして卒業試験を先生から勧められ春に卒業。当時、卒業試験は先生の推薦がないと受けられずとても難関でした。試験の初日は会場(大学内の広い教室)に入ると、教授がズラーッと並んで座っていらっしゃいました。
そして卒業試験を先生から勧められ春に卒業。当時、卒業試験は先生の推薦がないと受けられずとても難関でした。試験の初日は会場(大学内の広い教室)に入ると、教授がズラーッと並んで座っていらっしゃいました。
 試験曲は、
試験曲は、
バッハ・平均律より3曲
ベートーヴェン・ソナタの初期、中期、後期の中から1曲づつ3曲
但)初期のソナタは、ハイドン又はモーツァルトでも良い
その他違う作曲家の中からエチュードを3曲
例えば、ショパン、ドビュッシー、リストとか
ロマン派の作品を1曲、
近現代を1曲、
コンチェルト2曲
上記の課題曲より私が事前に提出した曲目の中から先生方が試験曲を選び、それを演奏するシステムでした。第2次試験は2週間後でした。
お客様も入り、会場は大学内のホールでした。第1次試験とは違う曲を45分~50分、自分でプログラムを組み立てて演奏するリサイタル形式で、この試験は演奏家としての資格を試されるとても厳しいものでした。他にも教える事を試される教師になる為の試験があり、こちらも又なかなか厳しい内容の様でした。この試験は、どちらかと言うと、その国の人達が主に受けておりました。
大学を卒業できた報告を致しましたところ、永井先生や両親から一度帰国し、勉強した成果を皆様へ御披露しなさいと言われ、日比谷公会堂にて「帰国記念コンサート」を開催致しました。永井先生のご紹介で新演奏家協会へマネージメントをお願いする事になり、先生もご挨拶にご一緒して下さいました。そして当時の社長・魚住源二(うおずみげんじ)氏がN響や他へ私の資料を渡し、各方面へ紹介して下さったようです。(つづく)
深沢亮子